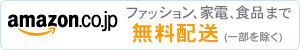複雑になっていく
前回のブログで、現代はアプリなどでバスの情報がわかったりと便利になってる一方で、高齢者には複雑になっているという話をしました。
今ちょうど読んでいる稲垣えみ子さん著「寂しい生活」の中に同じような記述がありました。
どの家も、家電だけじゃなくて、今やあらゆるものが溢れてパンパンです。こうしてさらに暮らしは複雑になっていく。多すぎるモノは、だんだん、人々の手に負えなくなってくる。
さらに記憶が乱れ始めた母は、新しい家電だけでなく、溢れ返ったモノたちに苦しめられるようになりました。
多機能すぎる
テレビのリモコンもいろんな機能がついていて、とってもわかりにくい!
地デジ、BS、CSなどの並んだボタンをうっかり押してしまった母から「テレビが映らない!」と何度か電話がありました。
(後日ホームセンターで簡単リモコンなるモノを購入)
でも、これって高齢者だけでなく、わたくしたち中高年だって同じです。
高度経済成長時代の真っ只中に育った中高年は親世代と同様に、新しい家電やモノを手に入れて生活が豊かになっていくという図式が当然だと思って生きてきました。
そして今、親世代と同じように、中高年も「モノ」に苦しめられています。
「モノ」は本当は生活を豊かにするためにあるのに、それに苦しめられるなんて、とても悲しいですね。
どうしてこうなってしまったのか
わたくしたちがモノをたくさん持ちすぎたから、モノに多くのことを求めすぎたから、なのでしょうか。
親のことも気になるけど、中高年も、まだ体も頭もまだしっかりしている今のうち、自分を本当に豊かにするモノは何か、ということを考えないといけません。
いや、考えてるヒマはないですよね。
すぐに片付けないと!
「寂しい生活」については、また書きます〜
では!